パートナー通信 No.55
非嫡出子相続分違憲判決(最高裁平25年9月4日大法廷)を受けて大塚武一(弁護士)
1 はじめに
このケースは、古くから違憲ではないかと議論されてきた非嫡出子の相続分の問題に、最高裁が違憲であると判断したものです。決定文は裁判所のホームページで公開されています。関心のある方は是非、全文を読んでみてください。非常にわかりやすく書かれていると思います。岡部裁判官の補足意見は、法律婚を尊重する意識と個人(子)について書かれています。
今回の最高裁の判断を一言でいうと、人間は両親を選んで生まれることはできません、したがって両親の婚姻関係の有る無しによって子の相続分が変化するのはおかしい、ということです。この一言だけをみると当たり前の判断じゃないか、なぜもっと早く判断されなかったかと思いませんか。実は、今回の非嫡出子の扱いの問題は、戦後、民法を改正しようという時(昭和22年)から、相続分を同じにしようと議論され続けてきた問題なのです。問題の中心は、わたしたちが『家族』と『個人』をどのように考えるか、です。
2 婚姻と子の相続分の説明
わたしたちの日本の民法には「婚姻は~届け出ることによって、その効力を生ずる」(民法739条1項)として、事実婚ではなくお役所に婚姻届を届けることによって法律上、夫婦となるとする法律婚主義を採用しています。そして、婚姻関係のある男女から産まれることを嫡出(ちゃくしゅつ)といい嫡出である子と嫡出でない子を区別しています。今回、違憲と判断された条文は、非嫡出の相続分は嫡出子の相続分の半分にするとしています(民法900条4号ただし書き前段)。
にもかかわらず、嫡出であろうとなかろうと「直系血族」であることにかわりはないので、「互いに扶(たす)け合う」(730条)、「扶養する義務」(877条1項)があるとされます。これは、嫡出でない子の父親に対する扶養義務を嫡出子と同様に認めるにもかかわらず、相続分は嫡出子の半分だということです。ううん。おかしいですね。
3 議論されてきた状況
では、なぜ、相続分について嫡出子のみが優遇されてきたのでしょうか。 かつて、今回と同じケースにつき裁判所は平成7年に、以下のように判断しています。民法が法律婚主義をとる以上、法定相続分は嫡出子を優遇し、他方、非嫡出子にも一定の相続分を認めてその保護を図ったものである。このように法定の相続分を定めることも立法府の合理的な裁量の範囲内と判断しました(最高裁平成7年7月5日大法廷)。裁判所は、国会、つまりわたしたち国民が議論して法律婚主義を採用し、これを尊重する相続制度をつくったとしても、国会の立法権の範囲内だと考え、また、非嫡出子を差別することにはならないと考えたのです。平成7年当時すくなくとも、非嫡出子の相続分に差を設けることは、法律婚の尊重の結果であり、国民が支持してきた以上仕方がないと考えてきたのです。また、平成7年当時の諸外国の法律に目を向けると、主要国でも非嫡出子の相続分に差を設ける扱いは残っていました。ドイツは平成10年、フランスは平成13年に改正されるまで、非嫡出子の相続分における差別は残っていました。
4 今回の裁判所の判断
それでは、今回、裁判所はどのように判断したのでしょうか。
- ① まず、家族法は国民の家族のあり方に対する考えを度外視して違憲性を考えることはできないとします。
- ② 続いて、時代とともに変わるわたしたちの家族に対する考えを詳細に検討します。そして、裁判所は、わたしたち国民の家族に対する考えは法律婚を尊重しつつも、家族の中の個人の生き方を尊重する意識が明確にされたと分析します。
- ③ そして、子は親の夫婦関係を選んで生まれてくることはできない以上、「子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」と判断しました。
この結果、本件規定を差別にあたるとして違憲としました。
5 日本の家族と個人に対する考えの変遷
裁判所のいうとおり、家族法は、わたしたちの伝統・風俗等が密接にからむ分野であり、わたしたちの家族に対する考えに支えられるものでなければ押しつけがましいものになってしまいます。
では、わたしたちの家族に対する考えはいったいどういったもので、どのように変わってきたのでしょうか。
日本の家族は、かつては家制度や家督相続に代表されるように、男子が受け継ぐ「家」を、また男の子に受け継がせていき、「家」を保っていくというふうに、家族集団として生きるものと考えられてきました。そこでは、個人よりも家族という集団が優先され、この考えに基づく立法がされてきました。
この考えは、戦後、憲法を新しくしたことを受けて、両性の本質的平等と個人の尊厳の原則に基づいて改正されなければならないとされますが(憲法24条2項)、昭和22年の戦後の民法大改正の際には家制度は廃止されましたが、非嫡出子の相続分は、法律婚を尊重する以上、当然、嫡出子より劣るという考えが残ってしまいました。実際の当時の改正議論では、意外なことに婦人委員のほとんど全員が非嫡出子の相続分を引き上げることに反対されたと記録されています(中川・改正経過48頁)。これに対して、当時の改正委員は「女として考えないで、本妻として考えているのであろう」(我妻・改正経過49頁)とコメントしています。
ここからわかることの一つとして、当時、お妾さんの存在が珍しくなく、また、男尊女卑の風土であったことから、非嫡出子の相続分を嫡出子と平等に扱うと、事実上、「妾の保護」になってしまい、男性が妾をつくるという封建制の名残を肯定してしまうのではないかと危惧した結果の思考です。
この時から、70年かけて、わたしたちの家族のあり方に対する考えは大きく変わりました。現代では、いわゆる晩婚化、非婚化、少子化が進み、これに伴い中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加しているとともに、未成年の子を持つ親の離婚件数や再婚件数も増加しています。また、シングルマザーとしてバリバリ働くキャリアウーマンも数多くいます。
こうして、われわれの家族に対する考えと実際の在り方が、憲法における家族に対する理念である個人の本質的平等と個人の尊厳の原理に無理なく整合してきたと判断した判例といえます。
6 これからの子どもの権利
今回、最高裁の決定によって、非嫡出子に対する相続分における差別が事実上、撤廃されることになりました。わたしたちの家族に対する考えは、多様化し個人の生き方を尊重する立場です。このことは、多様化された個人の生き方の下で生まれた子ども達には等しく差別なく扱うことが求められるという時代の要請を理解できると思います。
実際に、子どもは、自ら生活するようになるまで、長い間、親の保護が必要です。個人の生き方を尊重するとしても、子どもの発育よりも親の生き方を優先されてしまっては、元も子もありません。ここに、今回の最高裁の決定の優位性を認めることができます。
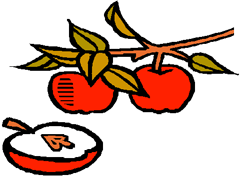







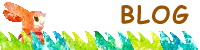
 ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
