パートナー通信 No.95
報告:県内自治体訪問③前橋市・小川 晶 市長を訪問
はじめに
昨年9月12日(木)前橋市を訪問し小川市長と懇談する機会を得ました。市側からは、市長と共にこども未来部長、こども支援課長、こども政策係長が同席され、群馬子どもの権利委員会からは、世話人8名が参加して、和やかな雰囲気での30分の懇談となりました。
最初に代表から、昨年2月11日に開催した「子どもまんなかフェスタ」に、市長就任前でしたが小川さんもご参加くださったことへの感謝を述べるとともに、私たち30年の歩みについての簡単な説明を行いました。
子どもの現状
今回の懇談では、小川市長が『前橋市子ども基本条例』制定を政策の一つに掲げていることから、テーマを「こども基本条例」に絞り、検討に反映されるよう参加世話人がそれぞれの活動や子どもの現状を報告しました。
◎インクルーシブ教育の充実
日本政府に対する国連勧告では、障害者教育の未だに分離された実態への懸念が述べられている。県ではインクルーシブ教育のモデル事業なども始まっている。市レベルでも一層充実した取り組みを進めてほしい。個々の子どもの発達のニーズを踏まえながら共に学んで行けることが求められている。
◎発達障害のある子どもへの支援
通常学級でも6%の子どもに発達障害の可能性があると言われているが、子どもの多様な事実に対する教職員、子ども同士、保護者の理解が求められている。とりわけ教職員の研修の充実が重要である。
◎子ども食堂に取り組んで
コロナ禍の下では一度にお弁当250食を提供したが、今は100食ほどになっている。子ども食堂がまさに子どものセーフティーネットになっているが、状況が良くなる兆しが全くない。目の前で生活の困窮化が進んでいると感じている。前橋市には25の子ども食堂があるが、多くはボランティアで取り組まれていて財政的に困難を抱え、助成金など行政からの継続的な支援を受けているがなお一層の支援が必要である。
◎子どもアドボカシーについて
子どもの意見表明を支援する活動で、「一時保護所」に通って子どもたちの声を聴いている。子どもの権利を知るためのカードゲームを作って活用している。「言っていいんだ」と分かると、自分のことをありのまま話してくれる現場をたくさん見てきている。条約12条「意見表明権の尊重」を子ども施策にしっかり位置付けてほしい。
◎DVと児童虐待について
児童養護施設で働いていた経験から、児童虐待の背景にDVの問題があるということを如実に感じている。子どもの権利擁護と同時に困難を抱えている大人の権利擁護も極めて大切である。
◎「聴いてもらえる権利」
話の中にも度々触れられていた「意見表明権」だが、「聴かれる権利」という捉え直しが進んでいる。0歳から始まってあらゆる発達段階に応じて子どもの思いや願いが積極的・日常的に見て取られ、聞き取られなければならない。
小川市長のお話から
- *今、こども基本条例やこども計画の策定に向けて動いているところ。まさに子どもたちの意見表明をすごく大事にしている。担当課では、待ちの姿勢ではなく話しやすい環境をどう作り出すか、年齢による違いなども考慮してワークショプなどもやり検討している。
- *「権利」について子どもの頃からよく知っていくことで、大人になってからも皆さんが理解していけるような前橋市になると良い。条例が出される時に合わせて権利について知ってもらうものも作ることになると思う。
- *前橋市は子どもが産まれる前からのお母さんへのケアなども丁寧に取り組まれていると思うが、さらに行き届くようにしていきたい。支援につながれないでいる人たちとの結び付きも大切な課題と思う。
- *子どもをとりまく個々の制度や施策が上手くつながり、可視化されるとより良くなる。
(文責:加藤彰男)







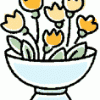
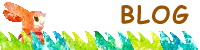
 ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
