パートナー通信 No.95
世話人会だより1日も登校しなかったけれど東京芸大大学院生として音楽家になった
当事者目線の記録 を読んで思ったこと 今村 井子
・はじめに
「本は心の財産」との自負があり、これまではできるだけ本を購入してきた。しかし、さすがに物価高騰、収入が激減。子育てにお金がかかる我が家(埼玉で下宿する大学生の息子と高校生の息子を二人抱えている)にとって、本は高価となり、最近ではもっぱら図書館で希望図書として購入してもらっている。表題のこの本も、新聞で話題との広告を見てから早速高崎市立中央図書館で購入希望を出したところ、即座に買ってもらい読了。やはり話題の本なのか、次の予約が入っているとのことで延滞禁止とのメールがあった。
・子どもにとって学校とは「行っても、行かなくてもいいところ」という衝撃
著者が本文やSNSで、この本を書こうと思ったきっかけとして何度か語っていることは「不登校でもなんとかなる」と言うことを自分の経験を元に知ってもらおうと思ったことのようだ。全国の不登校の子どもの数が激増している昨今、不登校の子どもを抱える親御さんが精神的に疲弊していたり、不安を増大させていることに対して、彼の経験を伝えることで、少しでも不安を払拭できたらとこれまで彼が経験してきたことが役に立つのではと思ったようだ。
「学校に行かない」という選択は、保護者にとっては漠然とした不安にはじまり、子どもの学習面や社会性、将来自立できるのか?などなどのネガティブなイメージがあり、それが結果的に家庭を追い詰め、子ども自身にとって家庭という居場所を奪いかねないともいえる。だからこそ、著者である彼は、身をもって「学校がすべてではないこと」、その時々で家族とともに「人生を切り開いてきた」きっかけがあったこと、学校以外にできることはたくさんあると訴えかけている。例えば、彼とその保護者がその時々においてフリースクールを活用したり、その時々で彼が周りと関わる中で考え学ぶ機会が保障されていたこと、そして彼が主張することをきちんと聞き尊重する大人がいたことは確かではないかと感じられた。知人のホームスクーラーがいたこともいい影響を与えていたのだと思う。だからこそ彼にとっての学校の意味は、「行くべき」と言えないうちは行かない選択もあり!としたのだろうと思う。不登校のネガティブな印象を一気にひっくり返しポジティブに変える、そんな力のある文章に心を揺さぶられたのはきっと私だけではないだろう。
・学校に通う意味を当事者(子ども)目線で問い直す
ただし、だからといって学校の存在意義をすべて否定するつもりはない。むしろ学校の教育的役割を子ども目線で作り直す時がきているのではないだろうか。子ども自身が「不登校」という選択をしていること(学校にNOを突きつけていることに)大人たちがもっと敏感であるべきでないだろうか。ようやく文科省も不登校は問題行動としないとの判断をしたのだから、「不登校対策」ではない、不登校の子どもの意見表明を知るためにも、この本はおすすめである。




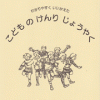



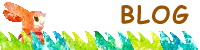
 ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
ここは「群馬子どもの権利委員会」や「こどもの権利条約」について、多くの皆さんに知っていただくためのサイトです。
